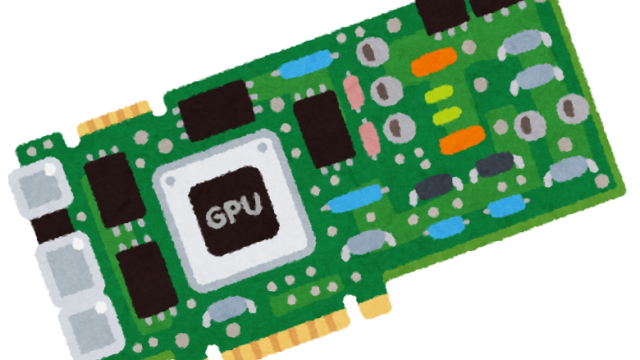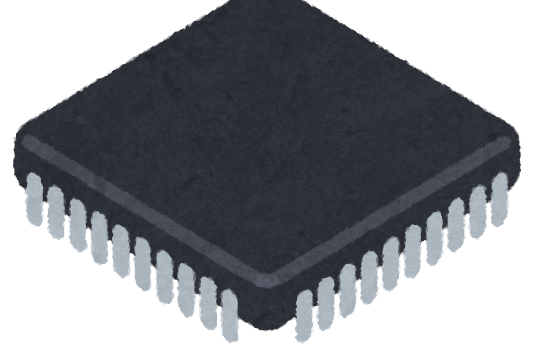日本の半導体の歴史
- 1940年代~1950年代:半導体素子の発明と研究
日本では戦後、アメリカから輸入された技術や文献をもとに、研究機関や大学で半導体の基礎研究が始まる。
日立製作所や東芝などの電機メーカーも、自社で半導体素子の開発を進める。 - 1960年代~1970年代:集積回路(IC)の登場と実用化
日本では、アメリカからライセンスを得たり、自社で開発したりして、IC(複数の半導体素子を一つの基板上に集積したもので、電子回路を小型化・高性能化)を製造する。
ICは、コンピューターや電卓などの応用製品に使われるようになる。
日本は、ICの量産技術や品質管理技術に優れており、アメリカや欧州に対して競争力を高める。 - 1980年代:DRAM(動的メモリ)の世界制覇と日米摩擦
DRAMは、コンピューターなどに必要なメモリ(記憶装置)である。
DRAMは、容量が大きく、消費電力が少ないという特徴がある。
日本は、DRAMの開発・製造に力を入れる。
DRAMは、高度なプロセス技術やパッケージング技術を要するため、日本の技術力が発揮される。
日本は、DRAMで世界シェアの上位を独占する。
特にNECや東芝などは、DRAMで大きな利益を得る。
しかし、アメリカは日本のDRAMに対して不満を持ち始める。
日本はダンピング(不当廉売)や特許侵害などを行っていると非難する。
日米間で貿易摩擦が起こり、日本はアメリカへのDRAM供給量や価格を制限することになる。
また、プラザ合意によって円高が進み、日本の半導体メーカーの収益は悪化する。 - 1990年代~2000年代:衰退と再編
日本の半導体メーカーは、DRAMの競争力を失っていく。
韓国や台湾などの新興国が、低コストで大量生産するようになる。
日本は、DRAM以外の分野にも進出しようとするが、成功しない。- 例えば、CPU(中央演算処理装置)では、インテルに敵わない。
フラッシュメモリでは、東芝が発明したものの、サムスンに追い抜かれる。
日本の半導体メーカーは、経営危機に陥る。
多くのメーカーが撤退や統合を余儀なくされる。 - 例えば、NECや日立や三菱電機などは、ルネサスエレクトロニクスに統合される。
東芝や富士通などは、メモリ事業を分離する。
- 例えば、CPU(中央演算処理装置)では、インテルに敵わない。
- 2010年代~現在:再生と変革
日本の半導体メーカーは、再生を目指す。
特に、自動車や医療などの分野でニッチな市場を狙う。- 例えば、ルネサスは、車載用マイコンで世界トップシェアを持つ。
ソニーは、イメージセンサーで世界トップシェアを持つ。
日本は、半導体製造装置や電子材料などの分野で強みを持つ。 - 例えば、東京エレクトロンや信越化学工業などは、世界トップシェアを持つ。
日本は、半導体産業の変革にも対応しようとする。 - 例えば、ARM(プロセッサ設計会社)を買収したソフトバンクグループや、半導体ファウンドリ(製造委託会社)を設立したキオクシアなどが挑戦している。
- 例えば、ルネサスは、車載用マイコンで世界トップシェアを持つ。