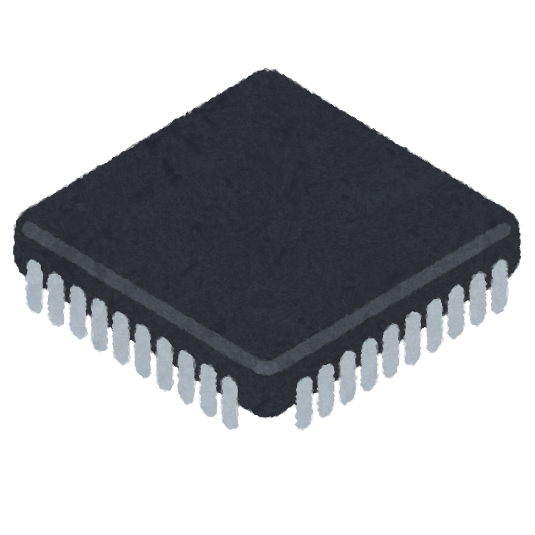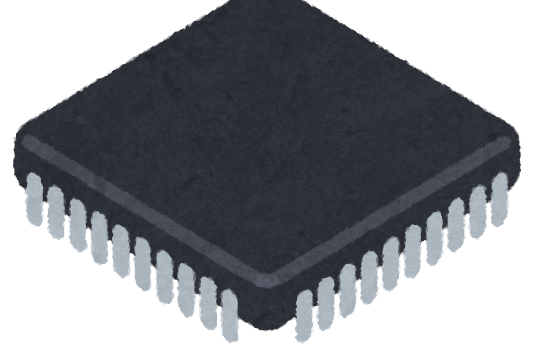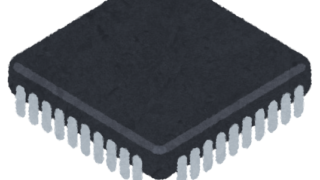メモリー半導体は、磁気や光学の記憶装置と比べて、データの読み書きが早く、記憶密度が高く、消費電力が少なく、振動に強いです。
記憶保持方法や書き換え方法によってさまざまな種類があります。
それぞれに応じて、容量や速度や耐久性などの性能が異なります。
記憶のアクセス方法によっても分類されます。
ランダムアクセスメモリは任意の位置のデータに素早くアクセスできますが、シーケンシャルアクセスメモリは順番にデータにアクセスする必要があります。
電源を切ってもデータが保持される不揮発性メモリと、電源を切るとデータが失われる揮発性メモリがあります。
それぞれに応じて、以下のような種類があります。
不揮発性メモリ
電源を切ってもデータが保持されるメモリで、主にデータの保存や転送に使われます。
以下のような種類があります 。
- フラッシュメモリ:電気的にデータを書き換えることができるメモリで、高速で大容量のデータを扱えます。
スマートフォンやデジタルカメラなどの内部記憶装置や、USBメモリやSDカードなどの外部記憶装置として使われます。 - ROM(Read-Only Memory):一度だけデータを書き込むことができるメモリで、書き換えることはできません。
安価で信頼性が高く、プログラムや固定データなどを保存するために使われます。 - EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory):電気的にデータを消去・書き込みすることができるメモリで、フラッシュメモリよりも書き換え回数が多く、小容量のデータを扱えます。
パソコンやプリンターなどの設定情報やパラメータなどを保存するために使われます。 - 3D NANDフラッシュメモリ:従来の平面的な構造ではなく、垂直方向に複数層のセルを積み重ねることで、高密度で大容量のデータを記憶できる技術です。
SSD(Solid State Drive)やスマートフォンなどの記憶装置として使われています 。 - ReRAM(Resistive Random Access Memory):電圧をかけることで抵抗値が変化し、データを記憶する技術です。
高速で低消費電力であり、書き換え回数も多いです。
AIやIoTなどの分野で活用される可能性があります 。 - MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory):磁気トンネル接合素子を用いて、磁気的にデータを記憶する技術です。
高速で低消費電力であり、耐熱性や耐放射線性も高いです。
自動車や航空宇宙などの分野で使われています 。
揮発性メモリ
電源を切るとデータが失われるメモリで、主にデータの処理や一時的な保持に使われます。
以下のような種類があります 。
- SRAM(Static Random Access Memory):トランジスタだけで構成されたメモリで、高速で低消費電力ですが、高価で容量が小さくなります。
CPUやキャッシュメモリなどの高速アクセスが必要な部分に使われます。 - DRAM(Dynamic Random Access Memory):トランジスタとコンデンサで構成されたメモリで、低価格で大容量ですが、低速で高消費電力です。
また、コンデンサの電荷が減少するため、定期的にリフレッシュする必要があります。
パソコンやスマートフォンなどの主記憶装置として使われます。 - DDR5 SDRAM(Double Data Rate 5 Synchronous Dynamic Random Access Memory):DDR4 SDRAMよりも高速で大容量のデータを扱える技術です。
パソコンやサーバーなどの主記憶装置として使われています 。 - HBM(High Bandwidth Memory):DRAMチップを垂直方向に積み重ねてシリコンインターポーザーと接続することで、高速で大容量のデータを扱える技術です。
GPUやAIプロセッサーなどの高性能計算装置として使われています 。