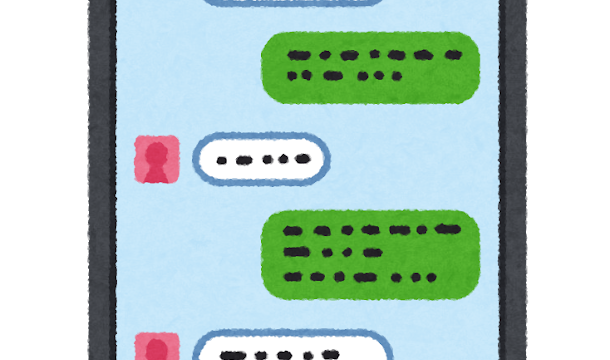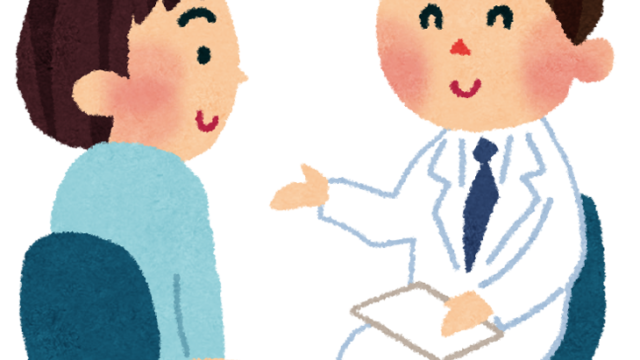AIとコンビニは、近年密接な関係になっています。
コンビニは人手不足や廃棄量の削減などの課題に直面しており、AIを活用して業務効率化や売上向上を図ろうとしています。
- 無人コンビニの導入:店員が不在でも商品の精算ができる仕組みを採用しているコンビニです。
カメラやセンサーが顧客の動きをトラッキングし、商品を手に取ったり棚に戻したりする動作を認識して、自動で会計を行います。
Amazon GoやJR高輪ゲートウェイ駅の無人コンビニが有名です。 - AI発注の導入:商品の発注をAIが自動で行う仕組みです。
販売データや天候、イベントなどの情報をもとに、最適な発注量を算出します。
ローソンのセミオート発注やセブンのAI発注が実施されています。
- 人手不足の解消と人件費の削減
店員が不在でも商品の精算ができる仕組みを採用しているため、人手不足や高齢化などの社会的課題に対応できます。
また、人件費や教育費などのコストも大幅に削減できます。 - 会計時間の短縮とレジ待ちの解消
ICタグやカメラなどの技術を用いて、商品の読み取りや精算を自動化しています。
これにより、顧客はレジに並ぶ必要がなく、スムーズに買い物ができます。
また、現金決済ではなく電子決済が主流になることで、現金管理や強盗対策などのリスクも低減できます。 - 商品の入れ替えや在庫管理の効率化
自動化された在庫管理により、迅速かつ柔軟に商品を入れ替えることが可能です。
顧客は常に新しい商品に触れ、新鮮なショッピング体験を楽しむことができます。
入店前に事前登録や本人確認を済ませる必要がある場合があります。
ウォークスルー型の無人コンビニでは、顔認証や社員証などで入店し、決済も同様に行います。
事前登録や本人確認の方法は、店舗によって異なりますので、注意してください。
セルフレジ型の無人コンビニでは、商品のバーコードを自分でスキャンし、電子マネーやクレジットカードで決済します。
現金決済はできない場合が多いですので、事前に確認してください。
店舗内に設置されたカメラやセンサーなどを壊さないようにしましょう。
無人コンビニでは、これらの機器が商品の読み取りや会計、防犯などに重要な役割を果たしています。
故意に損壊した場合は、法的な責任を問われる可能性があります。
- ローソンのセミオート発注
AIを活用した半自動発注システムのことです。- 人手不足や廃棄量の削減などの課題に対応するため、商品の発注をAIが自動で行う仕組みを導入しています。
- 過去の販売状況やポイントカードから得られる会員データ、他店舗の販売状況、天候、気温など100にも上る指標を用いて、最適な品揃えと商品別の発注数をAIが推奨してくれます。
店長や店員はその結果を確認し、必要に応じて修正することができます。 - 弁当、おにぎり、サンドイッチなどの商品に適用されています。
飲料、菓子、加工食品などの商品には、「計画発注」というシステムが適用されています。
計画発注では、基準在庫数を設定することにより、最適な発注数が算出されます。 - セミオート発注と計画発注の組み合わせにより、毎日の発注業務を短時間・的確に行えると同時に、廃棄ロスや販売機会ロスも削減できます。
- セブンのAI発注
AIを活用して商品の発注を自動化するシステムのことです。- セブンイレブン・ジャパンは、2023年春に全国の約2万1000店にAI発注を導入しました。
AI発注は、販売実績や共通催事、天気予報など、合計13の内部与件と外部与件の要素から最適な発注数を提案します。 - 発注作業にかかる時間を約4割減らせる。
AIが発注数を提案するので、店舗の発注担当者はその結果を確認するだけで発注が完了します。 - 顧客満足度や売上を向上させる。AIが顧客のニーズに応じた商品の品揃えと数量を提案することで、顧客は常に欲しい商品を購入できます。
- セブンイレブン・ジャパンは、2023年春に全国の約2万1000店にAI発注を導入しました。
AIがコンビニ店員の仕事を奪うことはないとは言い切れませんが、完全に置き換えることは難しいと思います。
AIやロボット技術は、コンビニ業界においても様々な分野で活用されていますが、それらは主に業務効率化や売上向上を目的としたものであり、人間の店員に代わってすべての仕事を行うものではありません。
店員が不在でも商品の精算ができる仕組みを採用していますが、品出しや客への案内などは人間が行わなければなりません。ただし、一部の商品では自動陳列ができるようになってきています。
商品の読み取りや会計端末などのシステムにトラブルが発生した場合にも、対応できる人材が必要です。
AI発注は商品の発注をAIが自動で行う仕組みですが、これも完全に人間の判断を排除するものではありません。
AI発注は販売データや天候、イベントなどの情報をもとに最適な発注量を算出しますが、店長や店員はその結果を確認し、必要に応じて修正することができます。
コンビニ店員として働く人々は、AIやロボット技術によって自分たちの仕事がどのように変わっていくかを把握し、その変化に対応する能力やスキルを身につける必要があるでしょう。
また、AIやロボット技術によって自分たちの仕事に付加価値を与える方法を考えることも重要です。
例えば、顧客とのコミュニケーションやサービス提供など、AIやロボットが行えない業務に注力し、顧客満足度を高めることです。
AIやロボット技術はコンビニ店員の仕事を奪うことはないでしょうが、変化に対応することは必要です。